| ●阿久比町次世代育成行動計画の概要がまとまりました |
 |
1 計画策定の趣旨
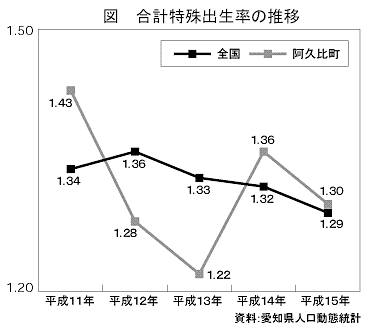
急速に少子化が進み、全国の子どもの数が戦後最低記録を更新している状況に対し、国では平成15年7月「次世代育成支援対策推進法」が成立するなど、その取り組みは本格化しています。
次世代育成支援対策推進法とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、国が定める行動計画策定指針に即して、地方公共団体・事業主が行動計画を策定することなどを定めた平成27年3月31日までの時限立法です。
阿久比町でも次世代育成対策推進法に基づいて、本町での取り組みの方向性、基本指針を明らかにして施策を拡充させます。
2 基本理念
子どもたちが健康で輝きながら育つまち 阿久比
●安心して子どもを生み育てやすい地域環境づくりを目指します。
●子どもの生きる力を育み、健やかな成長を支えるまちづくりを目指します。
●子どもの視点に立った安全なまちづくりを目指します。
3 阿久比町の現状
◆子育ての悩み
就学前・小学生の子どもをもつ保護者を対象としたニーズ調査結果をみると、子育てに関する不安と悩みがストレスとして蓄積している状況が浮かんできます。
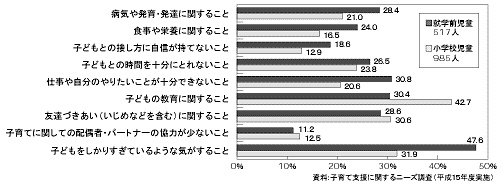
4 計画の施策体系(抜粋)
| 地域における子育ての支援 |
| (1)地域における子育て支援サービスの充実 |
●放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の充実
【実施箇所数】H16年度2カ所→H20年度3カ所
●休日保育事業の実施
【実施箇所数】H21年度1カ所
●つどいの広場事業の実施
【実施箇所数】H21年度1カ所 |
| (2)保育サービスの充実 |
●通常保育事業の推進
【定員数】H16年度660人→H17年度690人
●特定保育事業の実施
【実施箇所数】H19年度1カ所、H21年度2カ所 |
| (3)子育て支援のネットワークづくり |
| ●子育て支援総合ガイドブックの作成 |
| (4)児童の健全育成 |
●学校施設開放の促進
●児童館活動の充実 |
| 母性並びに乳幼児などの健康の確保および増進 |
| (1)子どもや母親の健康の確保 |
| ●乳幼児訪問指導の充実 |
| (2)食育の推進 |
| ●乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた食に関する学習の機会や情報提供の推進 |
| (3)思春期保健対策の充実 |
| ●思春期健康教育の推進 |
| (4)小児医療の充実 |
| ●小児救急医療体制の充実 |
| 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 |
| (1)次代の親の育成 |
| ●職場体験の充実 |
| (2)子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境などの整備 |
●基礎を理解する指導計画の改善・充実
●AET,少人数指導、TT指導の充実
●外部人材活用の充実
●教育相談体制の充実
●学校施設の整備 |
| (3)家庭や地域の教育力の向上 |
●子育て家庭教育に関する学習機会の充実
●親子で参加できるイベントの開催 |
| (4)子どもを取り巻く有害環境対策の推進 |
| ●青少年健全育成活動の推進 |
| 子育てを支援する生活環境の整備 |
| (1)良好な居住環境の確保 |
| ●宅地供給の促進 |
| (2)安全な道路交通環境の整備 |
| ●交通安全施設の整備 |
| (3)安心して外出できる環境の整備 |
| ●公共施設のバリアフリー化 |
| (4)安全・安心なまちづくりの推進など |
●公園施設などの整備
●防犯対策の充実
●地震災害などに対する取り組み |
| 職業生活と家庭生活との両立の推進 |
| (1)多様な働き方の実現および男性を含めた働き方の見直しなど |
●男女が働きやすい環境づくりセミナーの開催協力
●男女共同参画社会の必要性の啓発 |
| (2)仕事と子育ての両立の推進 |
| ●ファミリー・サポート・センター事業の検討 |
| 子どもなどの安全確保 |
| (1)子どもの交通安全を確保するための活動の推進 |
| ●交通安全教育の推進 |
| (2)子どもを犯罪などの被害から守るための活動の推進 |
| ●地域安全広報活動の推進 |
| (3)被害に遭った子どもの保護の推進 |
| ●相談体制の充実 |
| 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 |
| (1)児童虐待防止対策の充実 |
| ●虐待に関する相談窓口の充実 |
| (2)ひとり親家庭などの自立支援の推進 |
| ●母子家庭などの親への支援 |
| (3)障害児施策の実施 |
| ●障害児保育事業の充実 |
阿久比町次世代育成支援行動計画(PDF版)はこちらをご覧ください(約3MB)
クリックしても表示されない場合は、右クリックし、「対象をファイルに保存」(InternetExplorerの場合)などで一度パソコンに保存してからAcrobat
Readerで開いてみてください。
ご覧頂くためには、Adobe AcrobatReader 4.0(無償)以上が必要です。
導入されていない方は右のアイコンをクリックして、Adobe
Systemsの ホームページからダウンロードしてください。
■問い合わせ先 住民福祉課 TEL 48-1111(内301)
|