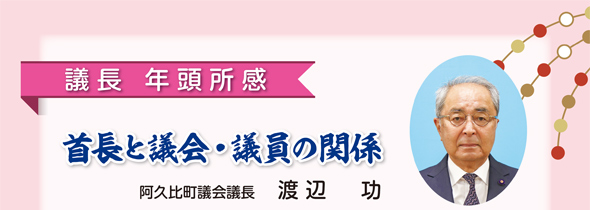
皆さまには、平素より町議会に対しまして、温かいご理解とご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
本町は、新しい町長が誕生し、本年1月には町制施行70周年の節目を迎えました。さらに1月14日に開催された愛知駅伝においては、町村の部で優勝し、市も含めた全体でも5位と大健闘しました。阿久比町の名が県内にとどろき、2023年新春は最高のスタートを切ることができました。
また、昨年12月18日の新町長就任を待ち開会した定例議会においては、所信表明を受け9名の議員が一般質問を行い、田中町長や竹内新教育長への期待も含め、公約や抱負等について質疑が展開されました。
知事選挙に続いて、4月には県議会や町議会の議員選挙が行われます。
地方自治体では、知事や市町村長などの首長も、議会の議員も、ともに直接選挙で選ばれます。首長と議会は対等な関係で、首長(行政側)が予算案や条例案などを作っても、議会の承認が得られなければ政策として実行できません。
自治体の行政は、議会のチェックのもとで運営され、これが「二元代表制」の仕組みで首長と議会は「車の両輪」にたとえられ、形式的には対等・平等とされています。
しかし実際には、首長の権能は極めて強く、行政の人事権や毎年の予算を決める決定権、土地利用の許認可権等を含め、政策立案から実施に至るまで一手に握ることとなります。
こうした背景もあり、多選をくりかえすと首長の専制化、独裁化が起こり、行政組織が硬直化する可能性が高くなる。さらには人事の停滞や側近政治により、職員の士気が低下する等の批判が出てくるものと考えられます。
一方、議員の任務は、住民要望の吸い上げや法律案・条例案などの審議決定を行うとともに、行政の業務執行を監視する役割を担っています。
さらに議会における大きな活動に、町の一般事務に対してその執行状況または将来の方針、政策的提言や行政の課題などを執行者に直接質す、一般質問があります。
しかし、時に住民からは予算や条例の提出権があり、強大な権限を持つ首長が圧倒的に優位ではないかとの声も聞かれます。
確かに、議会の議決事項は一見限定されているようにみえますが、いずれも重要事項であり、議会が多様な意見を反映しやすいことも独任制の首長にはない長所です。
二元代表制にあって、首長と議会が緊張関係を保ちながら、積極的な議論を通して政策形成の舞台となることこそが、町長のめざす「夢ある新しい阿久比町」の実現につながると考えます。