Q&A一般質問 >二井登喜男 議員
![]()

Q 児童虐待防止へ
A 個別支援を実施
![]()

赤ちゃんとのふれあいを
虐待で日常生活が恐怖とストレスにさらされた子どもは自尊の心を破壊され、これが子どもの問題行動の主要な原因ともなる。そこで伺う。
- 大事に至らないためのネットワークは。
- 発見から援助への行動。
- 予防と啓発。
- 加害者への対応、支援。
- 教職員への予防の研修。
- 助産師の出張授業、赤ちゃんとのふれあい体験などを提案したい。
![]()
- 関係機関で地域ネットワークを組織し、情報提供や情報交換をしている。
- 小中学校等からの通告等により、関係機関と協議し、必要に応じて個別支援を実施している。
- 乳児健診や園・学校での日常生活で異常の確認をし、チラシで子育て情報を提供している。
- こども総合支援センターを活用し、関係機関による相談を実施している。
- 保育士や教職員全員等で虐待予防を認識し、園内や校内で研修を実施している。
- 2分の1成人式に向けた学習の一つとして、6月下旬に助産師を招いて、4年生とその保護者を対象とした講演会を行い生命誕生のすばらしさ、命や精一杯生きることの大切さを話していただきます。
Q 脳脊髄液減少症への理解を
A 今後周知を検討
![]()
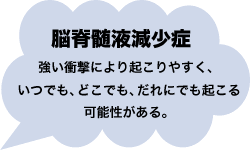
事故やスポーツ等で身体への強い衝撃により脳脊髄液が漏れて減少し、集中力、記憶力が減退し気力がなくなり、怠けととられ、周囲の理解が得られず、不登校となる児童、生徒も。いつでもだれでも、どこでも起りうる。町内への周知、学校現場での対応はどのように行っているのか伺う。
![]()
常日頃から児童生徒の健康状態等を注意深く見守っていますが、脳脊髄液減少症を広く認知するため、現職教育等の研修会で教職員への啓発を行います。
親の次に子どもの様子を把握しやすい担任の意識を高め、適切な対応ができるようにしていきます。
交通事故、スポーツ外傷などで脳脊髄液が漏れて、頭痛や首の痛みなどの症状を引き起こすもので、一般にはまだ認知されていないので、今後周知を考えていきます。