目指す子どもの姿と働きかけ 中学校3年生(15歳)
生活習慣
社会の一員として、自分の役割を自覚し、行動する生徒
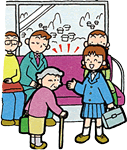
□ |
あいさつ(オアシス)が、場面に応じて正しくできる。 |
□ |
場面に応じた服装・態度を心掛けることができる。 |
□ |
公共の場や集団内で、周囲に配慮した言動をとることができる。 |
学習習慣
自ら進んで計画的に学習する生徒
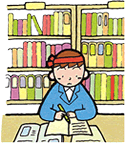
□ |
自分の目標を立て、その目標に向かって計画的に学習する。 |
□ |
進路について必要な情報を集め、それに向かって適切な準備をする。 |
食育
正しい食事のあり方を理解し、食事を通して自ら健康管理する生徒

|