固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に1度見直しを行います。平成18年度は、この評価替えの年にあたります。
今回の評価替えと税制改正に伴う固定資産税課税の主な変更点について説明します。
土地編
宅地比準土地(宅地・雑種地など)の税額の算定方法が変わります
平成8年度まで宅地などの税負担は、大部分の土地の課税標準額(固定資産税を算定する基礎となる価格固定資産税額=課税標準額×税率1.4%)が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきました。
平成9年度の評価替えからは、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が行われています。
宅地などについて負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。
平成18年度の評価替えの状況をみると、負担水準の均衡化が進んでいますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っています。
平成18年度から20年度までの税負担については、引き続き負担水準の均衡化を促進する措置をとります。
平成18年度の税制改正で18年度から20年度までの宅地などの税負担の調整の仕組みが、従来の方法と変わりました。
固定資産税を算出する基礎となる課税標準額の求め方を図示すると次のようになります。
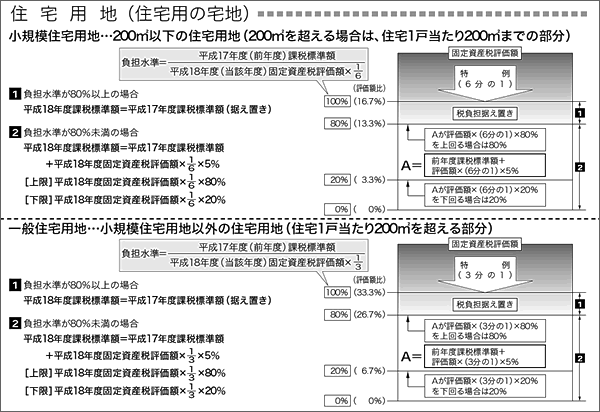
拡大図はこちら 住宅用地(84KB/84,281バイト)
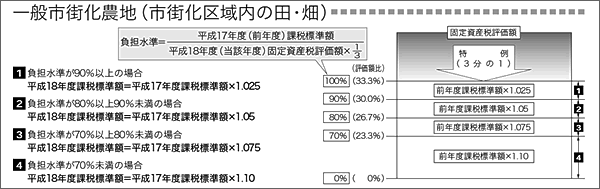
拡大図はこちら 一般市街化農地(40KB/39,299バイト)
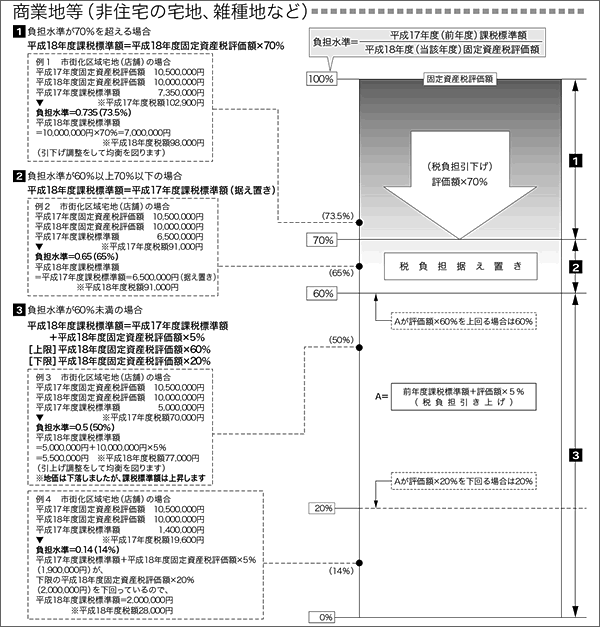
拡大図はこちら 商業地等(108KB/109,754バイト)
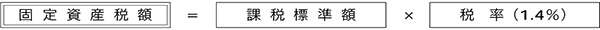
|