市街化調整区域内の宅地評価土地(宅地、雑種地など)の評価方法が変わります
阿久比町では、これまで市街化調整区域の宅地評価土地については、同じ状況類似地域(注1)内では、すべての宅地評価土地で標準宅地(注2)の価格からそれぞれの宅地の評価額を求める、その他の宅地評価法で評価してきました。
平成18年度評価替えから、市街化調整区域のすべての路線に路線価を付設し、その路線価を基にそれぞれの宅地の価格を求める市街地宅地評価法(路線価評価法)に変更します。
市街地宅地評価法では、それぞれの宅地周辺の街路状況を詳細に考慮し、これまでよりも公平な固定資産税評価ができるようになります。
市街地宅地評価法とその他の宅地評価法の違いは下図のようになります。
- (注1)状況類似地域
- 固定資産税評価で宅地などの利用状況が共通な地域を区分した地域です。
商業地域、住宅地域、村落地域などの用途の違い、幹線道路沿いやそれ以外の地域の違いなどで状況類似地域を分けています。
- (注2)標準宅地
- 地価公示や地価調査、不動産鑑定士による鑑定評価などを参考にその価格を決める宅地のこと。通常、それぞれの状況類似地域の中から標準的な宅地として1カ所選ばれます。
|
《その他の宅地評価法》
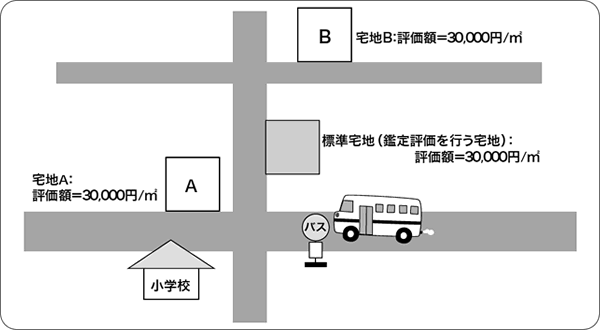
標準宅地の鑑定評価額が、30,000円/m2と決まると、道路の幅員や街路の状況に関係なく、同じ状況類似地域内の宅地A、Bの価格は、標準宅地と同じ30,000円/m2となります。
※実際の課税では、それぞれの宅地の形状(間口・奥行など)による補正を考慮した価格となりますが、この例では、標準宅地、宅地A、宅地Bとも同じ正方形の形状であると仮定します。

《市街地宅地評価法》
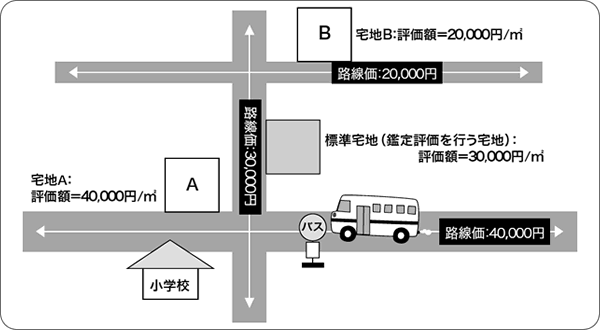
標準宅地の鑑定評価額が、30,000円/m2と決まると、標準宅地の接面する路線(主要な路線)の路線価は、30,000円/m2となります。
同じ状況類似地域内の他の路線は、主要な路線の価格と比較して、それぞれの路線の幅員、駅やバス停、公共施設や商業施設からの距離など、街路の状況を考慮してその価格が決められます。
例えば、宅地Aの接面する路線は主要な路線に比べ、幅員が広く、小学校やバス停からも近いため、その価格は主要な路線より高くなり、宅地Bの接面する路線は、主要な路線に比べ、幅員が狭く、小学校やバス停からも遠いため、その価格は主要な路線より安くなります。
※実際の課税では、それぞれの宅地の形状(間口・奥行など)による補正を考慮した価格となりますが、この例では、標準宅地、宅地A、宅地Bとも同じ正方形の形状であると仮定します。 |