ええじゃないか騒動
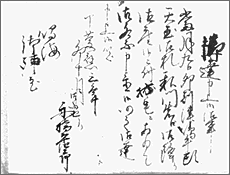
津島牛頭天王御札降り居留
(「要用記」) |
ええじゃないか騒動は、豊かな農民や商人、役人などの屋敷に神仏の御札や仏像が降ってきたのをきっかけに「ええじゃないか。ええじゃないか」とはやし言葉を繰り返し、人々が踊り歩いたというものです。
幕末のペリー来航以来、幕府の支配は急速に弱まりました。各地で倒幕運動が盛り上がり、全国的な凶作や長州征伐によって、米の値段が急激に上昇し、人々の暮らしは苦しくなっていました。このような不安定な情勢の中、三河地方から始まった「ええじゃないか騒動」は東は江戸から西は四国まで広がっていきました。
阿久比でも、慶応3(1867)年10月9日、山廻り役を務める宮津村の舟橋平四郎の門前に津島牛頭天王の御札が降りました。何者かが降らせた訳ですが、舟橋家では御札をまつり、酒やもちなどを供えました。うわさを聞いた人々が参拝と称して押しかけ「ええじゃないか」と、はやしたてながら踊り狂い、にぎわったと伝えられています。
記録は残っていませんが、大古根村の英比家にも御札が降ったと伝えられています。
騒動の根底にある「もっといい世の中になってほしい」、「少しでも生活が楽になってほしい」という人々の強い願いが「ええじゃないか騒動」を起こしたのではないかと考えられます。
(『阿久比町誌』参照) |