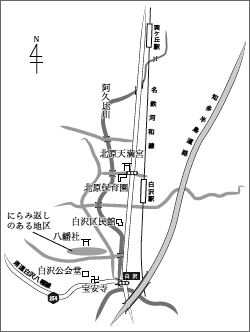

民家のベランダに取り付けられた
“にらみ返し”

にらみ返しの向かいにある“鬼瓦”

|
白沢地区の民家のベランダに、瓦製の怖い顔をした“小さな人形”が取り付けられる。道路を隔てた向かいの民家の鬼瓦をにらむ。
人形の正体は、中国から伝わる、疫病神を除くという魔よけの神「鍾馗」。にらみを利かせることで、隣家の鬼瓦によって除かれた災いが、自分の家に降りかからないようにと行われてきた風習で、その「鍾馗」を「にらみ返し」と呼ぶ。
ー 唐の玄宗は、科挙試験に失敗し、自らの命を絶った鍾馗を哀れみ、手厚く葬った。あるとき、玄宗が病に伏し、高熱に苦しみ悪夢を見る。虚耗という小鬼が現れ、楊貴妃の香袋と笛を盗もうとする。そこに鍾馗が現れ、帝に弔ってもらった恩返しにと、鬼退治をする。夢から覚めた玄宗の容態はすっかり良くなる ー
邪気が建物の中に入って来ないようにと、屋根の棟の両端に取り付けられる「鬼瓦」。寺の多い京都の町家では、「鬼瓦」からの邪気を追い払うため、鬼をも退治する「鍾馗」が、屋根に飾られる。事典を調べると、鍾馗の人形を大屋根や小屋根の軒先に飾る風習は、近畿〜中部地方で見られるとのこと。
地元に詳しい81歳の男性が「にらみ返し」について話してくれた。
「鍾馗さんが飾られる家は少なくなったねえ。この家は築5年くらいだけど、建て替え前の家にあった鍾馗さんを引き続き飾ったと聞いたよ。向かいの瓦に『水』とあるでしょ。あの鬼瓦をにらみ返しているんだよ」。
鬼瓦は鬼の形をしたものだけではない。「水」とあるのは家を火事から守るためだそうだ。
「隣の家同士、仲が悪かった訳ではないですよね」と友人がこっそりと言う。「それはないよ。皆さん近所同士仲がいいし、『にらみ返し』や『鬼瓦』のある家の人たちは、気さくで明るい人が多いよ」と男性が笑う。
「我が“鬼嫁”を、しっかりと、にらみ返しているんだけど、僕の言うことをなかなか聞いてくれないのはどうしてかなあ」。私が愚痴を言うと、「にらむ顔が、奥さんの目を見てないからじゃないですか」と友人に軽くかわされた。「にらみ返し」から目をそらし、空を仰いだ。青い夏空が広がっていた。 |