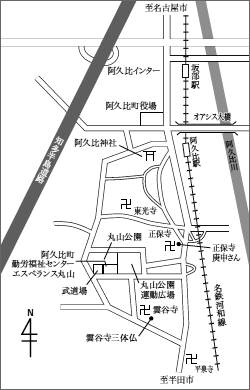

車の通りを見つめる“庚申さん”

中央が“歯痛地蔵”
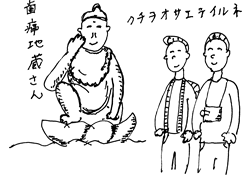 |
「夢を託した競馬の有馬記念は大敗。年末ジャンボ宝くじは惨敗。幸運の女神に会いたいよ。何かいいことないかなあ」。私の“ぼやき”を友人に聞いてもらいながら、2010年最初のぶらり旅をスタートさせた。
椋岡地区にある「正保寺庚申さん」を見る。「庚申堂」と記された看板が掲げられたお堂の中に高さ1m弱の石像が置かれる。『町文化財調査報告』では、大祭がうるう年の秋分の日に行われ、新しい鉄鍋などの金気の濁りを取り除くいわれがあると解説される。
石像は青面金剛像。庚申とは青面金剛の別称。『阿久比町誌』によれば、野ざらしになっていた石像に、子どもたちがいたずらをすると、たびたびたたりが起こったため、お堂を建ててまつったと記述がある。
中国に由来する民間信仰行事で、干支の庚申(かのえさる)の夜に、青面金剛像を徹夜してまつる「庚申講」がある。夜眠ってしまうと三尸(人の腹の中にいる3匹の虫)が罪を上帝に告げ、命を縮めるといわれる。
椋岡地区でも各家庭を持ち回る「庚申講」の組織が大正末期まで残っていたようだ。講元で青面金剛像をまつり、庚申の日には夕食を食べた後に、盗難防止や道の安全を願い念仏を唱えたとされる。(徹夜をしたかは定かではない)。
“庚申さん”は、役目を終えたという感じで、お堂の中から車の通りを静かに見つめている。ただ、心無い何者かのいたずらにより、本来青色でなければならない顔が、赤いスプレーで塗られているのは残念。庚申さんに「お疲れさま」と声を掛け、次に向かう。
場所を雲谷寺に移し、「雲谷寺三体仏」を見る。山門をくぐってすぐの境内西側に3体が並ぶ。きれいに整備された庭の砂礫を崩さないよう、飛び石伝いに、石仏の前へと進む。
3体は江戸時代に造られた。右手を右ほおにあてがう石仏が中央に座る。痛い歯を押さえているような珍しい姿。歯痛を治す仏だと伝わり“歯痛地蔵”と呼ばれ、今でも手を合わせに訪れる人がいるとのこと。
「いろいろな仏や神がいますよね」と友人が言う。「今年こそ幸運の女神を見つけたいなあ。なかなかほほ笑んでくれないけどね。君は?」。「新年早々開運の予感がします。近いうちにうれしい報告ができそうです」。その先が気になったが、友人はそれ以上話してくれなかった。 |