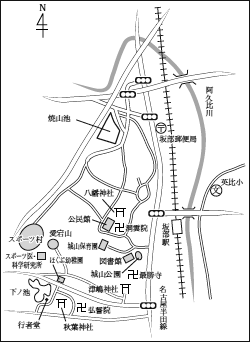

“水垢離”が行われた下ノ池

落書きをされ、“あるじ”がいない行者堂

|
下ノ池の周辺で「下之池垢離場行者像」を探す。ほくぶ幼稚園の正門付近から道を渡った場所に細道が続く。池に沿って歩くと、切妻屋根でコンクリート壁のお堂が見えてきた。
お堂に近づき中をのぞくと“あるじ”がいない。しかも壁にスプレーで落書きがされている。壁にはめ込まれた石に「下之池垢離場行者像」や「行者堂新設(昭和58年)」の記述が見られる。行者像が置かれていた場所に間違いない。
奈良県の大峰山に登る山岳修行がある。大正末期まで卯之山地区の若者は、大峰山に出掛ける前、遭難を避けるために、リーダー(先達)の下、白装束で下ノ池に入り、池の水で身を清めた。「水垢離」と呼ばれる儀式が7日間続けられた。
昭和51年に「卯之山同志講」が組織される。下ノ池での水垢離は行われなくなったが、心身を鍛える目的で峰入りが復活。どの時代も行者像に手を合わせてから、山へ向かうスタイルは変わらない。
「事件のにおいがしませんか」。友人が真剣な顔になる。消えた石像の行方を探すため、行者堂に刻まれた先達を訪ねることにした。
先達を務めた66歳の男性に、行者像のことを聞く。開口一番「たまらんわ」と肩を落とす。今年の8月に突然消えてしまったとのこと。心無い者がどこかへ持ち去ってしまったようだ。
「大峰山は若いころの良き思い出。毎年1回、険しい道のりを仲間で励まし合いながら登り、人生の修行になったよ。無事、山から戻ってこられたのも、行者さんのお陰だと思うなあ」
男性は昔を懐かしみ、行者像がいなくなったことを悲しむ。「早く見つかるといいですね」と声を掛け、再び池のほとりに戻る。
行者堂を新設して、行者像をまつるほど、信仰心の厚い人々の気持ちがこもった場所に、“あるじ”の姿が見られない。
池から冷たい風が吹き付ける。「皆さんのくやしさを考えると、やりきれないですよね」。友人の人間味あふれる言葉にうなずいた。 |