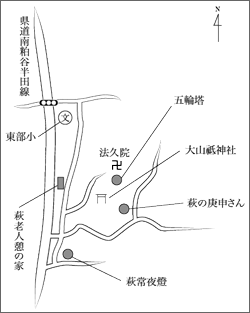

五輪塔の中央に「三つ葉葵の紋」

右のお堂に“庚申さん”が
安置されている
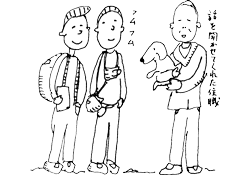 |
「萩常夜燈」へ行く。県道南粕谷半田線沿いのガソリンスタンド近くの一角に建つ。
萩地区の寄付者により、大正5年1月に造られた。土台の部分に石が積み上げられ、見上げるほど立ちの高い灯籠。
伊勢神宮への献灯目的で建造された常夜燈は、伊勢の国、現在の三重県を望む方角に「伊勢大神宮」と刻まれた文字が向けられている。灯りは昭和15年ころまで毎晩ともされていたようだ。
常夜燈のいわれを知る人がいないか探すために、細道を北へ向かう。地蔵がまつられるお堂の前で、楽しそうに会話をする2人の女性に出会う。年齢を聞くと79歳と73歳。
「まんだ私たち若いで、まっと年取った人に聞くと、ええかもよ」。「嫁いで、50年以上経つけど、詳しいことは知らんねえ。みんな待ち合わせ場所にしとるけどね」。
笑うと目尻にしわが寄る、とてもチャーミングな2人に話が聞けた。常夜燈の存在自体は薄らいでいるが、目印としての役割を果たしているようだ。
次に「萩の庚申さん」に向かった。通称萩の“スカイライン”と呼ばれるカーブの多い、坂道を上り切った場所左手に2つのお堂が並ぶ。西を向いて、右に「庚申像」、左に「役行者像」が安置される。1年に1度、地元の人たちで供養されているとのこと。高台から村人を見守り続ける“庚申さん”に手を合わせる。
最後に法久院を巡った。三つ葉葵の紋が石に刻まれた「五輪塔」がある。キノコのような形をした黒石の間に白い丸石を重ね、巨大な塔となっている。三つ葉葵が2カ所確認できる。
住職の話によれば、尾張藩の菩提寺の建中寺(名古屋市)から譲り受けたもので、黒石は尾張家の直系だけが使用する“伊豆石”とのこと。
「『この紋所が目に入らぬか』。水戸黄門の印籠(いんろう)と同じ葵の御紋ですね。『頭が高い、控えおろう』」。「君は助さんや格さんというよりか、うっかり八兵衛だろ」。「そう言われると自分も思いましたよ」。
次回につづく。 |