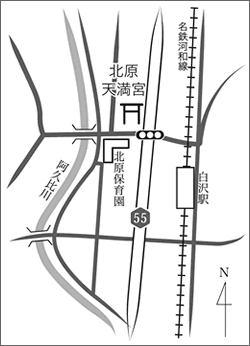

白沢地区の田園

片面にしか葉が付かない“片葉の葦”
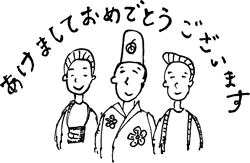
|
「英比麿が初めて荘内を巡視したとき、入江に大河が注ぐ河口付近は、広い沢地になっていました。そこには、丈の高い片葉の葦が一面に生い繁り、かれの来訪を歓迎するかのように、数百羽の白鷺が群れ遊んでおりました。かれは、その美しい景色に見とれて、長い間たたずんでいました。この地を『白沢』となずけよう、ここを開拓したら、きっとすばらしい美田となるに違いないと考えました。(阿久比の昔話)『英比麿物語』から」。
阿久比の郷を開いたといわれる英比麿。その英比麿が訪れたとされる伝説の地をぶらり旅に出掛けた。
英比麿の住居地跡だったとされる場所、北原天満宮に立ち寄り、西の方へと進む。阿久比川を挟み、田んぼが広がる。
友人が田んぼを見て「美しい田園が広がっていますね。英比麿さんのおかげですね。あと白鷺が出迎えてくれれば最高ですよね。田んぼに水がたまっているのは、沢地の名残りですかねえ」としみじみと話すので、私は「きのう、雨降ったよな」と軽いツッコミを入れて話を流す。
物語に登場する“片葉の葦”を探す。書物などで調べると、葦は「沼や川岸にはえる多年草」。片葉の葦は「茎の一方にだけ葉があるという葦の不思議を伝え、その由来を説く伝説が各地で、七不思議の1つと数えられている」とある。
散歩をする人たちに声を掛けるが誰も知らないと言う。インターネットで調べた写真が手掛かり。半ばあきらめかけ、北原保育園の西を流れる阿久比川の堤をのぞく。その瞬間「あれだ」と2人で大きな声を上げる。写真と見比べ「間違いないですよ」。「きっとそうだ。よね?…」。
一面に生い繁るとまでいかないが、川の堤の一角に群生している。確かに片葉だ。伝説の地に生えるといわれる片葉の葦が残るのは、やはり何かの因縁だろうか。英比麿が訪れる前に、何かこの地であったのかもしれないと、勝手に想像を膨らませてしまう。
友人が「ピタゴラスが確か『人間は考える葦』と言ってましたよね。それってどうゆう意味ですかね」と尋ねてくるので、「意味は知らないけど、ピタゴラスじゃなくてパスカルだったような気がするけどな…」と2人で首をかしげながら帰り道を急いだ。
次号も英比麿伝説を探しに出掛けます。 |