草木地区にある正盛院の仁王像を見に出かけた。
この寺にある仁王門(1752年建立)は昭和55年、仁王像(室町時代初期の作と推定)は昭和56年に町指定の文化財となっている。
石畳を登りきった場所に仁王門がどっしりとかまえている。両脇に太い柱が骨組みされ、柵の向こうに2体の仁王像が安置されている。
仁王門をのぞきこむと明かりがなく薄暗い中で、大きく目を見開いた仁王像が、一方は大きく口を開き、もう一方は口を固く結んでいる。表情からうかがえる迫力は、まさに阿吽(あうん)の呼吸で門番を務め上げているという言葉がよく似合う。
普段、悪いことをしているつもりはないが、思わず「ごめんなさい」と手を合わせて一礼してしまった。
「昔、寺は子どもの遊び場だったよ。親も子どもがいたずらをすると、仁王さんの前に連れていくぞと言えば、泣いて謝ったものだよ。今は子どももあまり遊びに来なくなったし、仁王さんと言っても、多分知らないだろうな」と笑いながら住職が話してくれた。
最近、幼い子どもが犠牲になる事件が相次ぎ、子を持つ親として大変心が痛む。仁王像は「悪を退治して、善を取り入れる」いわれがあるそうだ。時に仁王門から飛び出し、子どもたちに近づく悪を退治してもらいたいものだ。
寺の境内には、釣り鐘がある。毎年、大晦日の午後11時45分ころから除夜の鐘をつくそうだ。「煩悩の数、108回つくのが本当ですが、並んでくれた皆さん全員に鐘はついてもらいますよ。あなたたちも大晦日に来て鐘をついてくださいよ」と住職から誘いを受けた。2005年の反省をする意味も込めて、鐘をつきに出かけてみようかと思う。(毎年、その時間はこたつの中でうたた寝をしていびきがうるさく、妻に鼻をつままれる私。多分今年も……。)
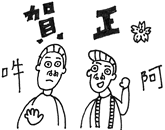 |