| ●シリーズ 阿久比を歩く 1 |
 |
| 知多四国八十八カ所 弘法参り |
 |
|

|
弘法堂を参る団体の人たち |
|
知多路の春は知多四国弘法参りで始まる。
3月になってから、町内で弘法参りと思われるバスやタクシーを多く見かけるようになった。
町内には知多四国八十八カ所の札所の寺が5カ所ある。
春の訪れとともに、弘法寺巡りをして阿久比のまちを足で歩いてみた。
|
3月5日(土)くもり。
日ごろ運動不足がちな友人を誘い、役場を出発点に第十三番札所板山地区の安楽寺まで歩くことにした。
オアシス大橋を渡り、阿久比団地を横目に目的地に向かった。福住地区に入り、田んぼの土手に目をやると”つくし”を発見。風が冷たく少し肌寒い日だったが、確実に春はそこまで来ていることを実感する。
目的地の安楽寺に到着。境内に一歩足を踏み入れると人影はなく、香の匂いが立ち込めている。中央にはいぶきの大樹がそびえたち、本堂、観音堂、弘法堂が整然と並び、いかにも寺という雰囲気が漂っていた。
 |
奉納経に朱印をする
竹田住職 |
せっかくのいい機会だと思い、「奉納経」を購入して朱印してもらうことにした。
さい銭をあげて本堂に手を合わせた。本尊の無量寿如来座像を眺めることができた。少し目を開けたふっくらとした顔立ちの仏像であった。
住職に許可を得て、建造物などを写真に撮らせてもらっていると、車で名古屋の西区から来たという老夫婦に出会った。
「毎年この時期になると、弘法さん参りをするのですか」と尋ねると、「今年の1月から始めたんだよ。2年ぐらいかけてゆっくり夫婦で八十八カ所巡ろうと思っているんだ」ときさくに答えてくれた。
そうこうしていると今度は、バスで訪れた20人ほどの団体に出会った。毎年弘法参りをしているような感じの人たち。弘法堂の前で般若心経を団体で唱え始めたので、後ろから一緒に拝ませてもらった。
安楽寺を後にして次に第十四番札所福住地区の興昌寺に向かった。
 |
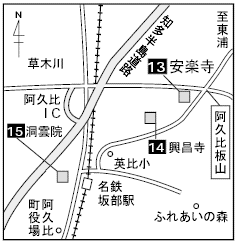 |
| 福山川沿道 |
福山川に沿って細い道を歩いた。この日は、暦のうえで「啓蟄」にあたる日だった。冬眠から覚めた虫たちが何かいるかと思い、下を見ながら足を進めた。
川ものぞいて見たが生き物らしきものはまだ発見できなかった。
今回から5回シリーズで阿久比の5つの札所を紹介します。
次回は興昌寺です。
(参考資料阿久比町誌・阿久比の寺院、あぐいのあゆみ、広辞苑)
◆板嶺山安楽寺
本尊は無量寿如来で曹洞宗に属する。
寺伝によると、文禄2年(1593)、洞雲院二世久山昌察大和尚を開山として創建。
慶安元年(1648)字川向安楽寺元居士敷から現在地に移転。
慶安・享保に続き、文化6年(1809)に8世玉峯僧山和尚によって再建。
現在の本堂・庫裡は、昭和57年9月に再建。
本尊 無量寿如来座像

恵心僧都作。名古屋市の服部氏から寄進されたもので年月不詳。
| 歴史解説 |
| 恵心僧都(源信) |
| ・・ |
平安中期の天台宗の僧。(942〜1017)「往生要集」を著して浄土教の基礎を築いた。 |
聖観世音菩薩立像
 |
 |
聖観音菩薩立像が
安置されている観音堂 |
9年ごとに開帳される秘仏 |
住職の話によると、行基菩薩の作と伝わり、普段は観音堂の中の厨子に納められて9年ごとに開帳される秘仏。
幼いころから足が不自由だった人がこの仏像に祈願をしたら全癒したとの話が伝わっている。
次回の開帳は平成20年。
| 歴史解説 |
| 行基 |
| ・・ |
奈良時代の僧。(668〜749)諸国を巡り、池堤設置・寺院建立・道路開拓・橋梁架設を行う。聖武天皇の依頼を受けて大仏造営にあたり、大僧正位を授けられる。 |
天白地蔵菩薩木像
 木像が納められている厨子 木像が納められている厨子
普段は地蔵堂の中の厨子に納められている。
耳の不自由な人が、穴の空いた柄杓を供え祈願をすると耳が聞こえるようになったという話が伝わり、明治・大正時代には、三河地方や伊勢方面の地名のある柄杓もよく見られた。
|